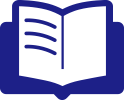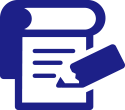2023年9月30日
2023年8月初旬、今回もベトナムで医療支援を行う眼科医服部匡志先生の元で医療ボランティア体験が実施され、YMS本科生からも高校生3名が参加しました。以下参加したYMS本科生からのレポートを紹介します。
高校2年 K.M.
3日間にわたって、服部先生の活動に参加させていただきました。
1日目はハノイから持っていく大量の医療物資を車に乗せるお手伝いをするところから始まりました。3時間かけて今回の活動先であるクアンニン省に移動し、服部先生と今回の医療スタッフの方々とお昼ご飯をご一緒させていただきました。ベトナム語は「ありがとう」や挨拶しかわからず、現地の方とコミュニケーションを取ることは難しかったですが、皆さん温かく受け入れてくださり、たくさん身振り手振り、話しかけてくださいました。
病院に戻るとすぐに手術着に着替えて、服部先生の回診に同行させていただきました。服部先生は患者さんの目をライトで照らし、白内障の進行具合を驚くべき速さで診断なさっていました。そして先生の指示を逃さないようにし、患者さんに抗生剤点眼薬やミドリンP点眼薬をさしました。最初の頃は作業に手こずりましたが、最終日の回診では1日目に比べるとスムーズに対処できました。
回診が終わると、手術室に戻り、患者さんの眼内レンズの準備を任されました。患者さんによってレンズの度数は異なり、体内に挿入されるものであるため、取り違いは許されません。責任を持って作業にあたり、計70ほどのレンズの準備をしました。
手術室では、主に白内障の手術が2列で行われていました。手術が終わった患者さんは片方の目が見えない状況なので、私が手術室を出て車椅子に乗せるところまで案内しました。手術中は、先生方、看護師さんたちの邪魔にならない様に注意を払い、手術を近い位置から見学させていただきました。白内障の手術は方法がわからないと見ていて今何をしているのか全くわからないので、スマホで大まかな手術方法を調べ、できるだけ多くのことを学び、吸収したいと思いました。結局1日目だけで30件の手術が完了しました。
1日目の活動が終わると、クアンニン省の幹部の方、医療スタッフを交えた夕食会がありました。ベトナムの飲み会の雰囲気を堪能しつつ、今回ボランティアを共にする仲間ともたくさんお話し、仲良くなることができました。
2日目は朝から鶏肉のフォーを食べて病院に向かいました。1日目に手術した患者さん、この日に手術する残りの患者さんの回診が終わると、そこから怒涛の40件以上の手術が休むことなく行われました。手術中の先生や看護師さんの動きを観察していると、手術が終わると同時に看護師さんがタリビット眼軟膏を目に入れていることに気づきました。次の手術のとき、勇気を振り絞って軟膏を手にして準備していると、チン先生が「やっていいよ」という表情をしてくださり、軟膏を目に入れ、腕に予め貼っていたテープでガーゼを止め、完璧なサポートができました。本当に嬉しかったです。
手術を手伝っていると、隣のオペ室で帝王切開が始まりました。手術室の外から覗いていると、服部先生が「見てきなよ」と仰ってくださり、間近でお産を見ることができました。人生で初めて見たお産は想像以上に感動的で、思わず泣いてしまいました。生まれてきた赤ちゃんは思っていたより血色感がなく、小さかったです。身体はとても小さかったですが、産声は非常に力強かったです。思ってもみなかった経験をすることができました。これも全て服部先生が呼び寄せた運、奇跡だと思います。
3日目も朝から牛肉のフォーを頂いて病院に向かいました。2日目に手術した患者さんの術後経過を見て回りました。一人ひとりにエースコックのハオハオを手術の成功を祝って手渡ししましたが、1個足りないという事件も発生しました。3日目は幸い再手術もなく、9時に活動は終わりました。病院のスタッフさんとも、写真を撮ったり、握手をしたりして、お別れの挨拶をしました。最後には服部先生の著作「人間は、人を助けるようにできている」の表紙裏に『情熱 2023.8.13』と書いていただきました。一生の思い出です。
[感じたこと]
今回の活動に参加する前は不安でいっぱいで、自分にできることなんて何もなく、迷惑をかけるだけだと思っていましたが、実際に現地で活動してみて、積極的に自分にできることを探しに行く姿勢が非常に大切であることを学びました。自ら行動を起こしてこそ得ることができることが、たくさんあることに気がつきました。学生である私にできることなんてたかが知れていますが、術前の緊張した患者さんをそっと支え、安心させることや、術後の患者さんに「お疲れ様でした!」と明るく声をかけることはできました。
先生は著作で『1人の人間としてどれだけ真剣に、そして医者としてどれだけ謙虚に患者さんのことを考えられるか。その心が何よりも大切だ。』とおっしゃっています。この言葉を胸に、初心を忘れず、患者さんから信頼される医師になれるよう、今回の経験を最大限に活かしていきたいです。
この度は私に、こんなにも貴重な経験をする機会を与えてくださり、本当にありがとうございました。
高校2年 H.M.
私が一歳の誕生日を迎えた頃、祖父は大腸癌を患った。診断はステージ4。その後、大手術を経ても更に癌は胃、肺と転移を繰り返し、その度に祖父は入院と退院、通院を繰り返した。祖父母に付き添っていた私にとって病院という場所が幼い時から身近だった。治ったかと思った癌が再発した際に、幼いながら大好きな祖父を助けられない自分の無力さを感じ、何かできないかと悔しい想いが常に心の根底にあった。私は、いつの頃からか記憶がないほど幼い頃から自分は医療を提供する側になるのだと決意していた。
ただ、医学の道を志すには、医学部受験という難関を突破しなければならない。想像していたよりも多くの課題と勉強量に非常に困難な道のりだと心が折れることが度々ある。諦めるのは一瞬で、とてもたやすいことだ。だからこそ、高い目標に向かって継続し、決して一歩も下がらない思いで立ち向かった者のみが許される門戸なのだとひしひしと感じる。
高2の夏を迎え、その道を私は走り抜けられるのか。今まで何の疑問にも思わなかった不安が押し寄せた。医学部受験の勉強への不安とともに湧き出た「私は果たして患者さんと医療従事者として向き合うことができるだろうか」という自問だ。この不安をぬぐうために実施でのボランティア活動を希望したが、コロナ禍の影響で日本では制約があり可能な場所を探すことができずにいた。
そんな不安の中、七沢先生のご紹介で服部匡志医師の下でボランティア活動ができると連絡を受けた。私は、絶好の機会を得ることになった。
服部医師は、2022年に長年ベトナムで白内障などの手術を無償で行った貢献をたたえられ、「アジアのノーベル賞」とも呼ばれるマグサイサイ賞を受賞している。その上で、活動のやりがいについて「自分が手術をすることによって光を取り戻してもらう、その患者さんの笑顔が僕にとっては最高のハピネスで、それはなかなかお金で買えるものじゃない。目が見えるということは、その人だけでなく家族全体が変わっていく。それが貧困からの脱出の手助けになればと思っている」と述べられた記事を目にした時、私の身体に衝撃が走った。十分な医療を受けられない環境にある方たちであればあるほど、その効果はその人の生活や仕事や家族や大事な命に直結する。なんて尊い仕事なのかと感動し、そのお手伝いができることに胸が高鳴った。
私たちは、ベトナムハノイから3時間半バスに揺られて、クアンニン省にある国立カンファ総合病院に向かった。気温は37度を超え、湿度がとても高く湿った空気と病院独特の消毒液の入り混じった匂いで、緊張が高まり、少し胸が詰まった。そんな重い空気の中、服部医師が私たちをまん丸の明るい笑顔で迎えてくれた。
まず、私たちが与えられたのは、手術をする患者さんのレンズの仕分け作業だった。友人とともに黙々とひたすら作業をしていると、今度は服部医師から点眼役の使い方の指導があり、すぐに患者さんの点眼実習を行うことになった。人に点眼するのは初めてだったが、思ったよりもうまくできたのがうれしかった。次に患者さんが利用するレンズの情報を書き込み、白内障の手術の準備を手伝った。手術後の患者さんが転倒しないようにと車椅子を手配し、しっかりと脇を抱えて術後の影響について観察をした。
服部医師が使用した後のガーゼやコットンを回収するためにゴミ箱を持って待機、移動し、医師の手術の様子を凝視するように観察した。患者さんはベトナム語だったので言葉は通じなかったが、微笑みかけてくれたので、私も「よかった」とホッとして自然と微笑み返していた。その瞬間、私の中で患者さんと向き合う自信という名の芽が生えたような気がした。
眼科のボランティアを経た後に、隣の病棟で帝王切開の手術に立ち会うことが許された。帝王切開手術の様子は目を見張るものがあり、胎盤は予想をはるかに超えて分厚く、血の海だった。周りの人は血が多くて怖いと少し引いていたが、私は生命の誕生という瞬間にこうして立ち会えていることにただただ感動し、目を見開いて観察した。
患者さん一人一人の生活と人生を幸福につなげるべく、服部医師、この病院のスタッフが一丸となり懸命にその任務を果たされる中で、末端ではありながらもその一端を担うことができたことは、かけがいのない経験となった。
この旅での最大の収穫は、『私自身のこの努力がほかの誰かの命を救うことにつながるならばどんな努力でも惜しまない』という決意ができたことだと思う。
これから押し寄せる不安とともに自分との闘いに負けそうなになった時、この思いを再度奮い立たせ、深い知識と熱い心を持ち、最良の医療を提供できる者を目指したいと思う。そしていつかベトナムの地に英知を備えて戻ってきたいと思う。
高校2年 I.N.
私はこの2023年の夏、ベトナムの医療ボランティアに参加し大変貴重な経験をしました。
このボランティアを通じて医師になるとはどういうことかを今まで以上に深く学びました。それは、大きく分けると3つあります。
1つ目は言葉が通じないということを理由に逃げないこと、そして、一人一人の患者さんに寄り添うことです。ボランティア初日は言語の壁が大きく衝撃を受け、あまり積極的に行動することが出来ませんでした。ベトナム語はとても難しく、患者さんとのコミニュケーションはジェスチャーや表情等だけでした。患者さんが何かを必死に伝えようとしていましたが、すぐには理解することが出来ず、この時に言語の重要性を実感しました。
しかし、言語が通じない状況でも目の前にいる患者さんは助けを待っています。また、患者さんは手術前後で不安でいっぱいです。そんな中、手当をする私がオドオドしていたら、患者さんをもっと不安にさせてしまいます。その為、患者さんに安心してもらえるように自分の行動に胸を張り、難しい状況下でも自分に出来る事を見つけ患者さんに尽くす事の大切さを学びました。
2つ目はやりがいです。白内障手術の術後経過で病棟を訪れました。患者さんがガーゼを取って視力が回復した瞳で、新たな世界を見て、喜びにあふれた満面の笑顔や家族の安堵した表情を見た時が、私が最もこのボランティアでやりがいを感じた瞬間でした。あの患者さんの笑顔は、たとえいくらお金を払っても人工的に再現することは不可能だと感じました。このやりがいを感じた事で残りのボランティア活動をもっともっと頑張ろうと思いました。
3つ目は医療チームの助け合いです。医師、看護師、パラメディカルといった医療スタッフ全員で患者さんをサポートしている姿に感銘を受けました。手術では、若い先生方に服部先生が直接指導しており、素晴らしい医療技術をベトナムの次世代へしっかりと引き継ぎ、ベトナムの医療技術向上にも大変尽力されている姿に感動しました。
今回、服部先生が、患者さん一人一人の心に寄り添っている姿を見て、眼科医である服部先生は眼だけでなく、患者さんの心も治療していると実感しました。今後この貴重な経験を存分に活かし大きく成長し、私に出来る事を通じて服部先生の素晴らしい医療活動をずっと継続して応援し続けていきたいと思います。大学生になったら再びベトナムボランティア活動に参加し服部先生に再会し、恩返しができるようにこれからも頑張っていきたいと思います。
最後に、このベトナム医療ボランティアで大変お世話になった服部先生、七沢先生はじめ、ベトナムの皆さん、支えてくれた両親、一緒に活動した方々に心から感謝しています。本当にありがとうございました。また服部先生に会える日を楽しみにしています。

ベトナムで医療支援を行う眼科医服部匡志先生とYMS生


術後の患者さんへ点眼薬を差す作業

現地の医療スタッフの方々と夕食会
◆眼科医 服部匡志医師経歴
2022年8月31日、「アジアのノーベル賞」とも呼ばれるマグサイサイ賞を受賞。20年間以上にわたり、白内障手術や網膜硝子体手術など約2万件以上を手がけるほか、若手医師の育成に従事、その貢献が評価された。ベトナムで「赤ひげ先生」と呼ばれ20年間医療活動を続ける眼科医。
高校2年生の時、父親を胃がんで亡くしたことが医者を志す転機となった。4浪の末京都府立医科大進学、1留し1993年に卒業。卒業後、眼科の木下教授に出会い、眼科の道に進み日本各地の病院で経験を積む。
2001年10月、京都府立医科大学で開催された「臨床眼科学会」でベトナム人医師と出会い、患者の治療と眼科医の指導を懇願される。網膜硝子体手術の分野ではトップレベルの技術を手にし、多忙でありながら医師として不自由の無い日本での生活を捨て、ベトナムでの医療活動を始めたのは、2002年4月。
赴任先は、医療指導という立場でベトナム国立眼科病院へ。網膜剥離や糖尿病網膜症などの治療、指導を始める。今では、服部医師が育てた眼科医も増え、ベトナムの眼科医療はレベルアップしてきたが、活動を始めた当初は、医療スタッフの教育や意識改革は進んでいるものの、器材不足は否めず、自腹を切って器具を買い揃えるため定期的に日本へ帰国し、資金を工面する二重生活を続けた。戸惑いや失敗も多く挫折を繰り返しながらも、現地の医療事情に適合しつつ実績を重ね、信頼を得ていった。
今やその技術は世界トップレベルで誰もが認める凄腕。20年間の活動で、養成してきた医師の数は、網膜硝子体手術では20~30人、白内障手術では40~50人。手術数は2万件を超える。
ベトナムでの国際貢献が認められ、これまで数々の栄誉ある賞を受賞している服部医師。2022年8月には、アジアの平和や発展に尽くした個人や団体に贈られ“アジアのノーベル賞”とも呼ばれる「マグサイサイ賞」を受賞。父親からの遺言は「人の役に立つ生き方をしろ」。学生などへの講演活動の際には、必ず「助けを求めている人がいたら、遠慮なく助けなさい」と伝えていると言う。服部医師の活動は今もなお続く。
YMS公式Facebook
https://ja-jp.facebook.com/YMS.yoyogi/
YMS公式Twitter
Follow @YMS_o
YMS公式Instagram
https://www.instagram.com/yms.web/