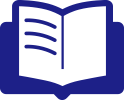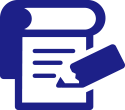2023年4月15日
1ヶ月前になりますが、2023年3月12日(日)、浅草ビューホテルにて東筋協研修ボランティアが開催され、医学部専門予備校YMSの生徒の中からも8名が参加しました。
東筋協とは、一般社団法人 東京進行性筋萎縮症協会の略称で、筋ジストロフィーなど、難病と向き合いながら生活をしている筋萎縮症患者とそのご家族を中心に設立され、難病でも住み慣れた地域で幸せに暮らせるように、患者と家族の医療・福祉の向上を目的として様々な活動を行っております。毎年、医学部専門予備校YMSの生徒も、車いす講習会や電車ハイク講習会等の貴重な会に参加させていただいております。近年新型コロナウイスルの蔓延によりZoomによる開催が続いておりましたが、今回ようやく対面での開催の運びとなり、YMSとしても嬉しい限りです。
以下、参加生徒2名からの研修レポートです。
◇とうきんきょうボランティアに参加して
山﨑 莉花
令和5年3月12日、兼ねてからお世話になっているとうきんきょうの会員の高見和幸さんからのお誘いを受け、浅草ビューホテルにてとうきんきょうの交流会に参加した。YMSからは私を含めて8人の生徒が招かれたが、皆それぞれに医学への目標を高くもつための良い経験となった。
11時にホテルに集まると、まもなくビュッフェ形式の会食がはじまった。円卓の席に座ると、生徒はそれぞれ近くの会の方々のお食事や移動の介助をしながら団欒する時間が始まった。看護学生の方々は、感染症拡大防止のために介助することが禁止されていたため、YMS生が大活躍した。またこのようなイベントも久しぶりに行われたため、会の方々も大変喜ばれていたのが印象的だった。私自身は以前に食事の介助を経験したことがあり、配慮すべきポイントや難しさを思い出していたが、なかにははじめて経験する人もいて、初めは緊張していたものの、次第に慣れて楽しそうに会話しながら上手く対応していて非常に立派に感じられた。以下に、私が今回ともに食事をしたとうきんきょう会長の三木 隆さんとの交流で感じたことを紹介する。
「円卓が低くて食べづらい」「フォークが重いので思うように動かしづらい」と三木さんは愚痴をこぼした。普段から不便なく生活している私には、テーブルが車椅子との高さに合わなかったり、食器や生活用品に使いづらさがあったりすることになかなか気づけず、そのような事実を改めて知ってボランティアに対する気持ちが引き締まった。
また、不自由なく生活する私たちと病を抱えて車椅子を使う生活を送られている方々との間には、視点のずれがあり、私たちが彼らの悩みや不便を知って歩み寄る姿勢が欠かせないと学んだ。さらに、私の考えとして、自分でできることは自分で、手伝うことは最小限であるべきだ、というものがあり、その程度を体感するために多くの会話が必要だと思った。それこそがボランティアの意義だとも感じられた。例えば、ビュッフェには美味しいパスタやリゾットなどがあり、ぜひ食べてもらいたいと考えた私はそれらを器によそうとすぐに、パスタもリゾットも食べにくいと考え直した。私が巻いて、口に入れて差し上げることは容易だが、もしかしたらやりすぎではないか?そこで、1口大に巻いたものをいくつか作ってお皿に乗せて差し出した。すると、「食べやすいねこれ」と喜んでもらえた。三木さんは基本的に自分の手で召し上がっていたが、「手が疲れてしまった」と教えてくださったので、食事の後半からお手伝いすることになった。正直のところ、はじめから私がお手伝いするべきだったのかもしれないと不安ではあるが、このようにしっかりとコミュニケーションをとることで、色々な工夫に気づけ、お互いが気持ちよくすごすことが出来るのだと思う。皆さん車椅子を使われているとはいえ、その大きさや形は人それぞれであり、また動きやすい、向きやすい方向なども個人差があり、よく会話をすることで、信頼も生まれてくるのだろう。
食事を終えて、会に参加されていた順天堂大学を卒業された医師の瀬尾さんが、東日本大震災時の銚子の様子についてお話ししてくださった。
2011年3月11日、瀬尾さんは研修医2年目で銚子の病院で働いていた。当時は景観を維持するという理由で、海沿いの津波対策がなされていなかった。大地震がおこり、7メートルの津波にのまれたという。大災害が起こったとき、自分で病院に来られる患者を救うこと以上に、動けずに自力で来られない患者を救わなければならず、しかし人手が足りないので研修医までが捜索に駆り出されて困難を極めていたそうだ。
瀬尾さんが外科医として研修を積んでいる最中で驚いたことは、病院が計画停電に巻き込まれたことだ。病院はすぐに自家発電に切り替わるのだが、切り替わる数分の間、手術室にいる人は暗闇に耐えなければならなかったそうだ。それ以来、患者には全身麻酔中に停電が起こるかもしれないという説明をするようになったという。
4月から6月にかけては、病院の再建や多くの患者の治療で忙しかったが、不思議なことに、普段の傾向として更に患者数が増加する8月と9月の時期に患者はほとんど来なかった。町の人々は、震災から復興しようと生活や町を立て直すのに忙しくしていたのだ。なかには、身体の不調や異変を感じながらも頑張って働き続けた人もいただろう。翌年、ステージがかなり進行しているがん患者が激増した。無理をしていた人々にしわ寄せがきたのだ。瀬尾さんは毎日末期のがん患者を診察して、もう少し早く病院に来てくれたら……という、患者を助けきれない無常観、震災直後とは違うその後数年続く別の苦難がある、と感じた。
東日本大震災からおよそ10年が経って、昨今は新型コロナウイルスの大流行という新たな困難の時期にみまわれている。パンデミックの最初期から数年経過した今、コロナで長らく病院に来られなかった影響で、震災時と同様に重症の状態で来る患者が増加しているそうだ。「医療従事者として患者と接するうえで、その患者は身体を犠牲にしてどのような状況下にあったのか、またさらなる身体に及ぶ危険はないか、そういった個人のバックグラウンドまで視野に入れ、自身のなにか気づけていない点を真剣に模索し考えていくことが必要です。」と教えてくださった。
続いて、とうきんきょうの会員である田沼さんが、コロナ禍での思いをお話された。田沼さんは院内感染で新型コロナウイルスに罹患され、非常に苦しい思いをされたそうだ。死亡する人も少なからずいる感染症は、身体が不自由な方々にとって肺や気管支など呼吸器の運動が低下するため、より一層恐怖に感じるものである。なかには、人工呼吸器を普段から使用している人もいるように、肺の疾病が命に関わるのだ。
しかし、今年あたりから徐々にコロナの脅威が薄まっていき、人々が外に出て活動するような動きに変わってきていて、そのような私たちの恐怖が一般の人々に知られなくなっていくのではないか。「コロナは終わったというイメージがあるが、依然として恐怖に思っている人もいるということを頭にいれておいてほしい。」と田沼さんは言った。
交流会に参加し様々な話を聴いた全体の感想として、常に周りをよく見て視野を広げ、自分の盲点に気づくことが大切であると改めて感じた。私はYMSを卒業し、今年度から医学部の1年生として医学の道へ踏み出したところである。これからも、仲間とともに社会に目を向け様々なバックグラウンドをもった多くの人と交流をもち、良い医師になるために修行を積んでいきたい。
最後に、お世話になったとうきんきょうの方々とお土産の焼売まで下さった三木会長、順天堂大学の看護学生の方々とOGの医師、看護師の方々、一緒に参加したYMSの仲間たちへ、非常に有意義で貴重な時間をありがとうございました。今後の活動も喜んで参加したいと楽しみにしています。
髙橋 紀勝
この度は東京進行性筋萎縮症協会の集まりに招待頂き、ありがとうございました。YMSの同輩である山﨑の働きかけによって私は参加することができました。代表者であられる三木さん、2年前からお世話になっている高見さん、同じ席であられた遠藤家の方々や会員の方々、それに順天堂の先輩方にお会いできて嬉しかったです。ありがとうございました。私はYMSの大屋と共に、当会の会員であられる遠藤駿介さんとその家族の方々とお話をしましたが、そこではどのように病気が発覚したか、病院でどのような事が起こったのか、そしてその後の経過までを事細かに知ることができました。そのお話はただ単に日々の苦労や心配事を知るだけでなく、我々YMS生として、医師を目指す者として改めてハッとさせられる言葉でもありました。
そして何よりも、車椅子を使用される方と”その家族”のお話を初めて聞けたことは大きく心に残りました。バイク乗りで快活な性格であられる父と、息子さんと夫にそっと寄り添う母からの言葉には、直接大変であるという言葉は出てきませんでしたが、普通の学校に通われていらっしゃった駿介さんの苦労や、家族の苦労を裏で感じ取ることができました。病気が発覚するまで病院をハシゴしたというエピソードや、階段しかない小学校や中学校に、車椅子の為に昇降機を持ち込む必要があったこと、さらにその送り迎えやヘルパーさんのことなど、様々なエピソードの中には相当な苦労と覚悟があったのだと察せられ途方もない気持ちになりました。
しかし、それでも元気いっぱいに振る舞う父の存在があるからこそ、家族に笑顔が生まれているのだと思ったし、あらゆる支えをして慎重さを欠かさない母の存在があるからこそ、家族を確実にまとめることができ、それらを真に理解する駿介さんがいるからこそ、家族全員が前を向いてるのだと思いました。私が同席して目の前にした家族は、同会に所属しているとか関係なく、家族として輝いて見えました。
私はこの度、浪人という長い足踏みを終え医学部に入ることができました。勉強で辛かった浪人中に実際に患者さんの方々と向き合う機会を頂けている私は、その度に患者さんに希望を与え続けられる医師になりたいという夢を改めて持ち直し、その夢に向かって頑張ることができていました。きっと医学生の間も、医師となってからも、様々な挫折や苦労を感じるでしょう。それでも、この実際に患者さんと向き合えた日を思い出して辛抱強く頑張れる自信がつきました。遠藤さん、高見さん、三木さん、そして同会の方々には感謝してもしきれません。新しく決まった医学部は少し遠いですが、密接に関わりたいと考えています。
この度は貴重な経験をありがとうございました。

研修会会場の様子


東筋協研修ボランティア参加の皆さんと記念撮影
東京進行性筋萎縮症協会のみなさま、ありがとうございました。
YMS公式Facebook
https://ja-jp.facebook.com/YMS.yoyogi/
YMS公式Twitter
Follow @YMS_o
YMS公式Instagram
https://www.instagram.com/yms.web/